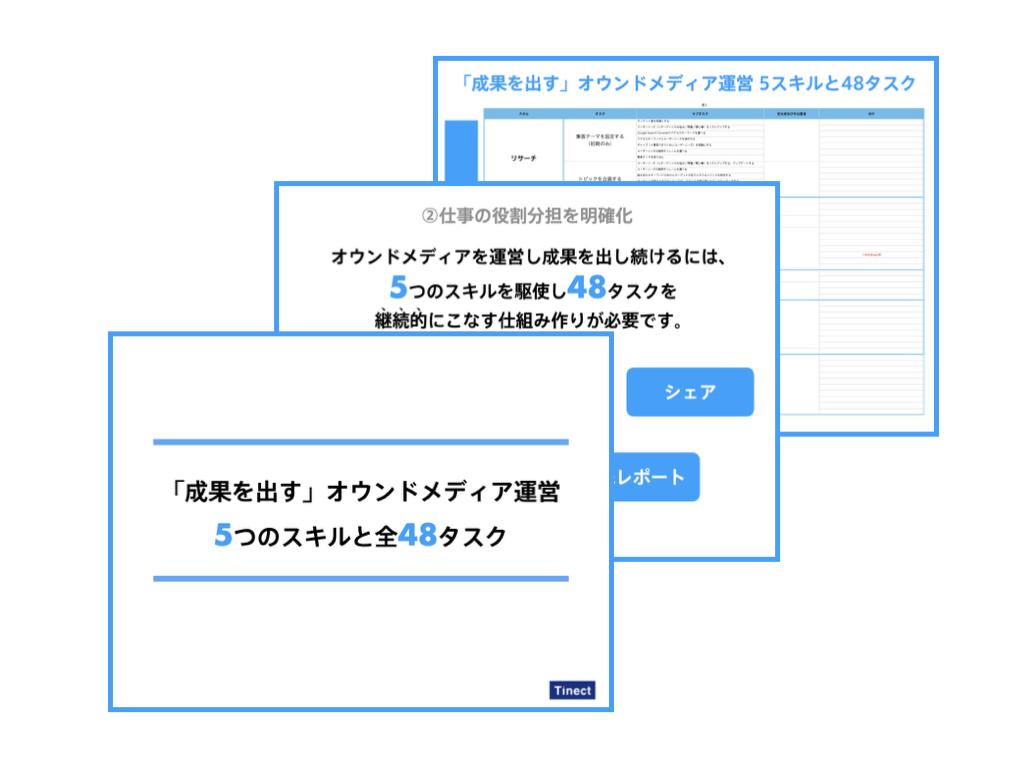このコンテンツは有料note「webライターとメディア運営者の、実践的教科書(安達裕哉著)」より転載しています。

一般的に本は、一部の時事ネタ、および最新の科学的知見などを除けば、最新のものにあまり価値はない。
歴史の風雪に耐えてきた文章ほど、普遍的で重要な事柄について書いてあるると考えてよいからだ。
ブラック・スワンで知られている、ナシーム・ニコラス・タレブは「20年以内のものはできるだけ読むな。ただし50年以上前のことを書い書いている歴史書は別だ」と述べている。
したがって、時間があれば「最近の本」に手を出すのもやぶさかではないが、基本的には「古い本」から読むと得られるものが多い。
ところが「文章術」という話になってくると、若干話は変わってくる。
それは、文章の媒体が変化しているからだ。
昔は「紙」に「万年筆」で書いた原稿を、「印刷」した「本」で読むのが普通だったが、現在では、「スクリーン」に「キーボード」で書いた原稿を、web上で「スマートフォン」を使って読む。
楽器が変わると音楽が変化するように、文章もツールが変われば変化して当然だ。
たとえばスマートフォンでは感情表現に「顔文字」を使うことが可能だが、紙媒体への印刷では、通常顔文字は使わない。
そういうことで、少なくともweb登場前の「文章術」とweb登場後の「文章術」とは、クラシック音楽とロックンロールくらいの違いがあると考えてもよいのである。
ただし、クラシック音楽の技法を、ロックンロールに持ち込んではいけない、という法はない。
むしろ、温故知新により、クラシック音楽の技法をロックンロールに生かせれば、新しいジャンルを切り開くきっかけになり得る。
そういう理由で、最近は「古い著名作家」の書いた文章術を少しずつ研究している。
そして、研究してみると、今でも十分通用する教訓、すなわち50年から100年くらいは変わらずに「本質」だと言えるようなことも見つかる。
そこで、今回はその中でも最も有名な、谷崎潤一郎の「文章読本 (中公文庫)」について、役に立ちそうな話をピックアップしたい。
谷崎潤一郎の「文章読本」
谷崎潤一郎の「文章読本」は、文章術の本の中でももっとも古いものの一つであり、1934年に書かれたこの本は、現代の文章術の先駆けと言ってもよい。
谷崎潤一郎の文章読本を受けて、川端康成、三島由紀夫らが同タイトルの本を出しているくらいだ。
「ものを書く」ことが、一部の上流階級の行為であった時代から、大衆の行為となるのがこのころから、と考えてもよいのだろう。実際、谷崎潤一郎がこの本の中で述べているノウハウは、非常に簡潔、かつ実用的なものだ。
では、内容の紹介だ。
序論
まず谷崎は、「小説に使う文章で、他の実用に役立たない文章はない」と、実用的な文章と芸術的な文章の区別はないことについて述べている。
とかく実用的な文章を学ぶときには「小説を書くわけではない」と強調されるが、双方は同じもの、と谷崎は主張する。
つぎに、文章は視覚的な要素も重要だということ。
例えばあえてカタカナで書いたり、ひらがなで書いたりすることも、フォントや理解の助けになるようなら積極的にやるべき、という話だ。さらに谷崎は「音調の美」と表現して、音読した時のリズムも重要だ、と述べている。
そのうえで谷崎は「文章の上達方法」の原則について述べている。
文章の上達方法の原則
ー文法にこだわる必要はない。
例えば、ある程度文章が書けるようなら、いちいち主語を明示せず、日本語本来の簡素な文章を書くほうが良い。
文章の目的は「理解させること」にある。
ー「名文」の条件は一律に決定できない
「文章はこうあるべき」を一律に決めてしまうことのは良くない。
たとえるならば、文章の味というものは、芸の味、食物の味などと同じである。
ー文章の上達は「多く読むこと」と「実際に自分で書いてみること」
したがって、文章の技能を上達させるには、定型的なことを覚えてもそれほど役に立たない、というのだ。
ではどうするか、と言えば、それは手本を見て、練習を繰り返すことにある。
文章の上達は理論的なものではなく、感覚的なもの。
理屈に依存して、練習をせずにうまくなろうとするのは、無理だという。
古来からの名文と呼ばれるものを、できるだけ多く読むこと。
その際には「乱読」より「繰り返し」が重要で、暗唱できるくらいまで読むこと。
また良い文かどうかを見極めるためにも「自分で書いてみる経験」は非常に重要である。
なおこれは、「名文家」として知られる、アメリカ合衆国の建国の父の一人であるベンジャミン・フランクリンの文章上達の方法とぴたりと一致する。
このころたまたま私はスペクテイター紙(一七一一年アディソンとスティールがロンドンで創刊した日刊紙。翌一二年廃刊)の半端物を見つけた。第三巻だったが、この新聞はそれまでに一巻も見たことがなかった。私はこれを買い求めて再三熟読しているうちに、大変面白く思われてき、立派な文章だから、できれば真似てみたいと考えた。その目的から、同紙の文章をいくつか選び出し、一つ一つの文の意味について簡単な覚え書を作り、そしてそれを数日間放っておいてから、今度は本を見ないで、頭に浮んで来る適当な言葉を使って覚え書にしておいた意味を引延し、原文にできるだけ近く表現しながら、もとの文章に戻すことを試みた。それから原文と私の書いた文章とを比べ、誤りを見つけては訂正した。すると私は自分がいかに言葉を知らないか、また知っている言葉でもやすやすとは思い出して使えぬことに気がつき、もし詩を作りつづけていたら、とうの昔にそんなことはできるようになっていたろうと思った。
とはいえ、指針が何もないのは心もとない、ということで、次に谷崎が触れているのは「文の要素別のアドバイス」である。
用語(言葉の選択)について
用語は「わかりやすく」「なじみがあり」「昔からある言葉を使う」こと。耳慣れない言葉をできるだけ使わないようにすることが重要である。
ただし言葉の選択には非常に気を使うべきで、「言霊」という言葉がある通り、使う言葉によって、思考が制限されてしまう恐れもある。
人間が言葉を使うと同時に、言葉も人間を使うのだ。
文の5種類の「調子」
ー流麗な調子。
これは源氏物語のように、長いセンテンスをつなげて書くこと。文章が流れるようにつながることで、流麗さが出る。
簡潔さはないが、日本文の特徴を発揮した文体である。
これは泉鏡花、里見弴、宇野浩二、佐藤春夫が体現しており、彼らの文章を読むと良い。
現代では「簡潔さ」がよしとされることが多いが、谷崎はむしろ「せっかく日本語で書くのならば、流麗な調子で」と勧めているようである。
ー簡潔な調子
これは前述した流麗な調子とは正反対の性格を持つ文章で、漢文調である。手本は志賀直哉。
叙述をできるだけ引き締め、字数をできるだけ減らし、内容を圧縮する。文末は「た」で終わるようにすると、「のである」よりも間延びせず良い。
ー冷静な調子
これは、学者肌の人に多い文体である。
谷崎は「カントの文章は乾燥した輝きを帯びているそうだ」と述べているが、哲学者全般の書く文章がそれにあたる。
作家では、夏目漱石の倫敦塔、森鴎外の山椒大夫、高瀬舟なども、この文体で書かれた作品の一つだ。
「戦争でも爆発でも、噴火でも地震でも、悉く粛然たる静止状態となって再現される」と谷崎は表現している。
ー飄逸な(のびのびした)調子
南方熊楠の随筆や、三宅雪嶺の論文の文章がこれにあたる。これは一つ目の流麗な調子の変化したもので、ひょうひょうとしてとらえどころのない調子だ。
物欲がなく、名文を書いてやろう、という野心がない人が、この文体で書けると谷崎は言う。
ーゴツゴツした調子
読者が一気に読み進められないように、「故意に読みづらいように書く」ためのものだ。一語一語に意を止めさせるための文章である。
ゴツゴツ派の作家は、簡潔派の文章ですら、なお流麗に過ぎると感じ、リズムを努めて無愛想に、不愉快にする。
これには一種「悪文の魅力」があり、読者をひきつけることがある。
谷崎によれば、天成のゴツゴツ派は、滝井折柴一人だそうだ。
文体は4種類を使い分ける
ー講義体
実際の口語に最も遠い文体。
センテンスの終わりに「のである」「のであった」「のだ」「だった」等を付け加えて、強める。
日常、個人を相手に話すときにこのような話し方はしないが、大勢の聴衆を前にしてしゃべるとき、殊に、教師が教壇に立って講義をする場合には、これを使う。
なお、明治大正期における諸文豪の散文文学は、悉くこの文体である。
ー兵語体
軍隊において兵士が上官にものをいう時に用いられる。
「である」「であった」の代わりに、「であります」「でありました」を加える。
礼儀深さと、慇懃さを体現する文体であり、講義体よりも親しみや優しさを感じられる。
中里介山の「大菩薩峠」や、本書、谷崎潤一郎の「文章読本」がこの文体で書かれている。
ー口上体
兵語体よりもいっそう丁寧な言い方。
主として都会人が改まった席へ出て口上を述べ、挨拶を交わすときによく用いられている。
「であります」「でありました」の代わりに「ございます」「ございました」を使う。丁寧ではあるが、くどい言い方になりがち。
ー会話体
平素、話をする際に使われている言い方。
「話すように書く」を体現した文体。
センテンスの終わりは内容によって変化する。
「彼は毎日学校へ通う」という言葉を、文脈によって
「通っているさ」
「通うんでね」
「通いますよ」
「通うんだからなあ」
と、いろいろに変化させる。
これらの音は、文章にない要素を補い、書いた人の声音や眼つきを想像させる役割を果たす。
言い回しが自由でセンテンスの終わりの音に変化があり、男女の区別もつけやすいことから、「文章はしゃべるように書け」という佐藤春夫のアドバイスはこの長所に基づいたものだろう、と谷崎は言う。
なお、谷崎が推奨しているのは「会話体」である。「話すように書く」のは、文章の味を出しやすいからだ。
自由に書いているブロガーさんたちの中には、会話体の方が結構いる。
4つの「体裁」に気を留める
文章の「体裁」とは、文章の視覚要素のこと。具体的には4種類ある。
ー振り仮名、及び送り仮名の問題
芥川龍之介は「読者に一番親切なのは、すべてに振り仮名をつけること」と述べたそうだ。
作者にとっても、往々にして「難しい語」より「簡単な語」のほうが、作者の予期しない読み間違いが多く、本意ではない読まれ方をしてしまうことがある。
そのため、基本的には振り仮名は「あったほうが安全」ではある。
ただし、すべてに振り仮名を振ることは、活字面の美しさを大半犠牲にしなければならなくなる。
また、振り仮名は「文の調子」によっても影響度が異なる。
たとえば流麗な調子の文章は、一字一字をはっきりさせて読むことを必要としない。全体をなだらかに読んでもらうことが重要なので、振り仮名との相性が比較的良い。
逆に字面がシンプルであることが重要な「簡潔な調子」との相性は悪い。
難しい漢字が使われていることそのものが、「効果」でもあるので、振り仮名は望ましくない。
このようなことから、現実的には「やむを得ない場合」に振り仮名を振る、という選択肢になる。
ー漢字及び仮名の宛て方
読み方を字面だけ見ても分からない語がある。例えば
生物 (いきもの? せいぶつ?)
生花 (いけばな? せいか?)
出入 (でいり? しゅつにゅう?)
といった具合だ。
したがって、こうした語を、訓で読んでもらいたい場合には、
生き物
生け花
出入り
と、送り仮名を振るのがわかりやすい。
ところが、このルールがすべてに通じるかというと、
請負 ⇒ 請け負い
場合 ⇒ 場合い
子守 ⇒ 子守り
など、送り仮名をしないほうが良い場合などもあり、ややこしい。
このような表記に関して最も気を使っているのが、森鴎外である。
鴎外は文章の記法を一貫させ、その言葉の由来にさかのぼって語源の上から正しい文字を宛てる、という手間をかけており、谷崎は「彼の文芸作品を渉猟して、その文章の構成法、用語法などを調べたら、立派な口語文法の書物ができるのでは」と述べている。
ただし、この方法も万能ではなく、最終的に谷崎は「文章の視覚的、音楽的効果として扱う」と結論付けている。
つまり、語調と字形の美観の方からチェックする、という具合だ。
例えばわかりやすく書きたいなら「振る舞い」と書き、特殊な情調を重んじたいときには「振舞」と書く。
谷崎は「盲目物語」という小説を書いたとき、なるべく漢字を使わず、大部分をひらがなで書いた。それは、戦国時代の盲目の按摩が年老いてから自分の過去を語る体裁になっていたからだ。
「老人が、おぼろげな記憶をたどりながら、しわがれた、聞き取りにくい声で、ぽつりぽつり語る」を表現したかったと谷崎はいう。
なお、谷崎は最後に、大阪毎日新聞社の「スタイル・ブック」という小冊子を薦めている。
大阪毎日新聞社では、自分の社の新聞に用いる宛て字や仮名使いの法則を定め、スタイル・ブックと題する小冊子を編んで、社員や関係者に配ったことがありましたが、あれはなかなか実際的で、穏当な意見であったと思いますから、あれを入手される御便宜がありましたら、御参考までに御覧になることをおすすめいたします。
なかなか面白そうではあるが、現在はいくつかの大学などの図書館にしか収蔵されていないようなので、なかなか閲覧の機会は限られているが、機会があれば見てみたいと思う。
ー活字の形態(フォント)
谷崎が執筆を行った当時は、文章と言えば「活字」による印刷が中心だったが、フォントの概念についても谷崎は触れている。
端的に言えば振り仮名をふってもごちゃごちゃしにくい「フォントは大きめ」が谷崎の推奨のようだ。
ー句読点
まず谷崎の前提として、「句読点の打ち方に普遍的に通用するルールはない」がある。
したがって谷崎は、これも送り仮名などと同様に、感覚的効果として扱うことを推奨している。
「読者が読み下すときに、調子の上から、そこで一と息入れてもらいたい場所に打つことにしている」と谷崎は述べているが、その息の短いところに読点(、)やや長い時に句点(。)を打つ。
この使い方はセンテンスの構成と一致することが多い。
が、必ずしも一致するわけではない。あえて技巧的に、句読点を使わないときもある。
例えば、以下は谷崎が春琴抄で取り組んだ、句読点の使い方である。

これだけの長さの文章に対して、句読点はわずかしかない。谷崎はこれを
・センテンスの切れ目をぼかす
・文章の息を長くする
・薄墨ですらすらと書き流したような、淡い、弱々しい心持を出す
という目的で行ったと述べている。
日常の、あるいはビジネス文書でこういった技巧的な文章を使う方はあまりいないと思うが、ブログなどで試行してみても面白いかもしれない。
ー疑問符・感嘆符・引用符
欧米では必ず疑問や感嘆のセンテンスには打つというルールになっているが、日本では必ずしも用いるわけではない。
谷崎は「日本人は、声を上げて叫んだり、押しつけがましく尋ねるのは品の良いこととは思わない国民だ」と言い、控えめにすべきだと述べる。
ただし「知らない?」「知ってる?」といった、否定形、肯定系と同一の形の質問文については、疑問符があったほうが読みやすい。
なお、引用符は横書きの時は良いが、縦書きでは鍵括弧を使うべきである。
品格のある文章の作りかた
谷崎は「品格」を、イコール「礼儀作法」と捉えていた。
したがって、文章にも礼儀が必要であり、それを文章の品格、と定義している。
では、文章上で礼儀を保つにはどのようにしたらよいのか。
谷崎は「文章は精神の発露」と言い、まずはそれにふさわしい精神を涵養すべし、という。
そしてその精神を言葉で表すと「優雅」となる。
優雅とは、できるだけ己を出しすぎないようにし、自分を昔の偉い人たちの陰に隠すようにすることだ。それがすなわち品格、礼儀を体現する文章、ということになる。
では具体的には何をすべきか。
ー饒舌を慎む
谷崎には「言語や文章はただ物事を暗示するだけの働きしかない」という考え方がある。
したがって「はっきりと書く」のは、品格があるとはいえず、明白に言えることであっても、あえて遠まわしに匂わせるほうが良い、と彼は述べている。
例えば「伊勢物語」にある挿話はどれも「昔男ありけり」から始まっており、それらの男の姓名も、身分も、住所も、年齢も記していない。
同様に源氏物語の人名である「桐壺」や「夕顔」も本当の名前ではなく、ゆかりのある部屋の名や花の名を持って呼んでいるだけである。
ある意味では「報道」とは逆の概念と言ってもよいだろう。
叙述が理詰めであればあるほど、1から100までの説明を要するから、必然的に「理詰め」「事実のそのままの描写」を重視すればするほど、品格は損なわれる、と谷崎は考えてたようだ。
また、谷崎は実践的な指南として、無駄な形容詞や副詞は、「饒舌」にあたるから、極力省くべきであると述べており、「言葉を惜しんで使え」と述べている。
ー言葉遣いを粗略にしない
といっても、なんでもシンプルに書けばよい、という話ではない。
特に言葉の丁寧さに関しては、それを略してはならない、と谷崎は述べている。例えば、
してた × していた 〇
てなこと × というようなこと 〇
つまんない × つまらない 〇
あるもんか × あるものか 〇
もんだ × ものだ 〇
そいから × それから 〇
これは「口で話すとき」にも丁寧さがないと判断されるため、文章にしても同じことだ、と谷崎は断じている。
ー敬語や尊称を疎かにしない
敬語の扱いは難しいが、それをぞんざいに扱うことは、品位があるとは言えない。
少なくとも、尊敬語、謙譲語については正しく取り扱わなくてはならない。そもそも、尊敬している人の名前や代名詞などは、軽々しく口にすべきではない。
また「講義体」は言葉が強く、敬語を使うのに不適切な文体であり、兵語体、口上体、会話体のいずれかを選択するのが良い。
—
【お知らせ】
Books&Apps及び20社以上のオウンドメディア運用支援で得られた知見をもとに、実際我々ティネクト(Books&Apps運営企業)が実行している全48タスクを公開します。
「成果を出す」オウンドメディア運営 5つのスキルと全48タスク
をプレゼント。
これからオウンドメディアをはじめる企業さま、現在運用中の企業さま全てにお役に立つ資料です。ぜひご活用ください。
資料ダウンロードページはこちら↓
https://tinect.jp/library/5skills48tasks/
メールアドレス宛てに資料が自動送信されます。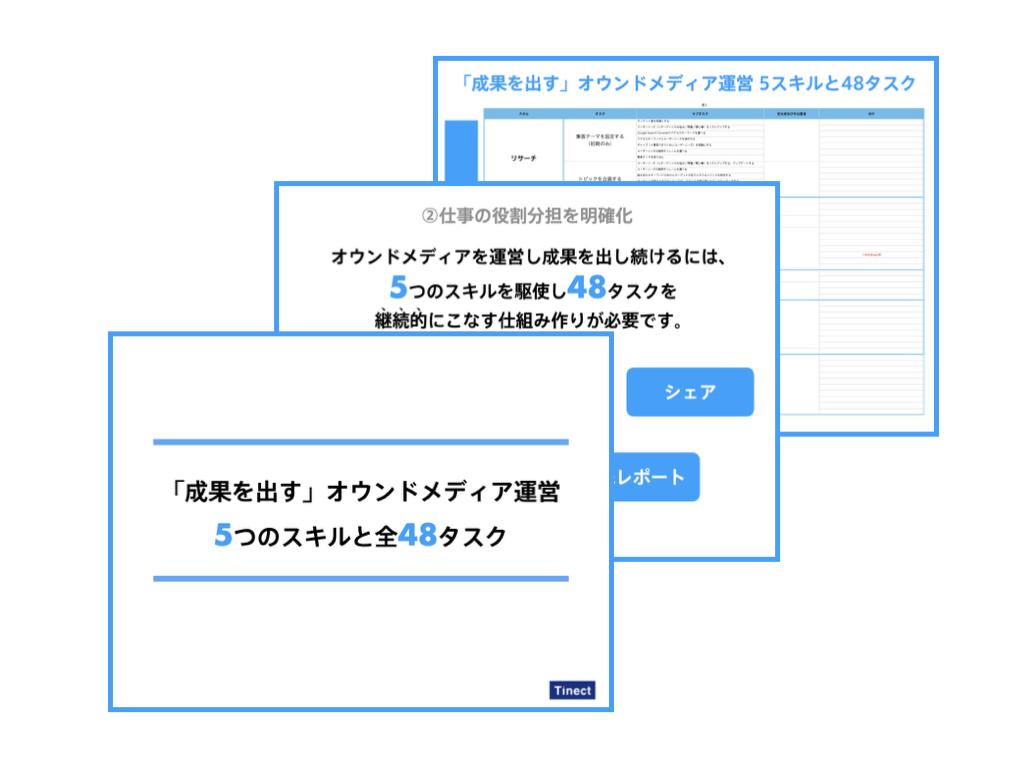
「成果を出す」オウンドメディア運営 5つのスキルと全48タスク
をプレゼント。
これからオウンドメディアをはじめる企業さま、現在運用中の企業さま全てにお役に立つ資料です。ぜひご活用ください。
資料ダウンロードページはこちら↓
https://tinect.jp/library/5skills48tasks/
メールアドレス宛てに資料が自動送信されます。