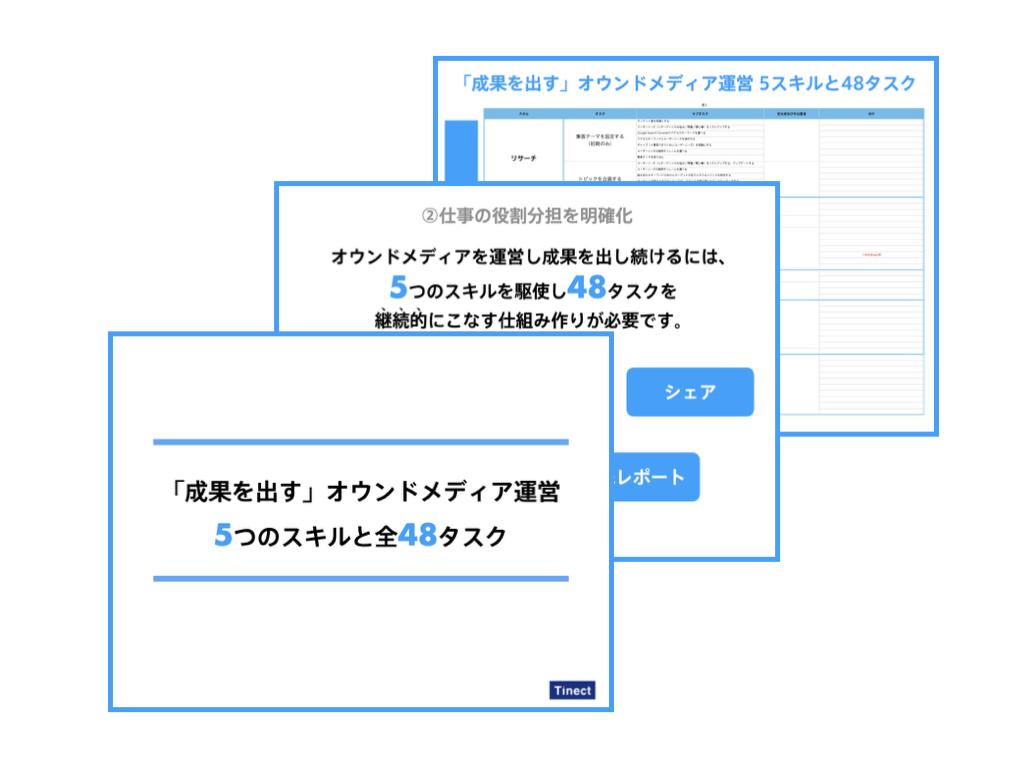このコンテンツは有料note「webライターとメディア運営者の、実践的教科書(安達裕哉著)」より転載しています。
メディア運営をするにあたって、最初の壁が「マネタイズ」であることは言うまでもない。
ダボス会議で「世界のメディア・リーダー100人」に選出された、メディア論の第一人者、ジェフ・ジャービスは、メディア企業が利益をあげることの重要性を説く。
重要なのは持続性である。これはつまり、情報を提供し続けられるだけの利益があがるかどうかということだ。だが、ただインターネット普及以降に失われた収益を何かのかたちで取り戻せばいいというものではない。少ない収益でも持続できるよう、効率化をする必要がある。以前のような独占が望めない今は、無駄を省いて組織の規模をできる限り小さくすべきだろう。また、大切なのは、情報に価値を付加して人々に提供することである。そうすることではじめてジャーナリズムは自らの存続に必要な利益が得られるようになる。(デジタル・ジャーナリズムは稼げるか ジェフ・ジャービス 東洋経済新報社)
稼げない企業は市場から退場せねばならない。それは鉄の掟である。
同様に、稼げないメディアにも存在価値はなく、退場せねばならない。税金で運営されるようなメディアは、大本営発表しかできない。
しかし、インターネットの登場により、情報の流通の独占が崩れた結果、従来のマスメディアが有していた「広告による収益」モデルは危機に瀕している。
現在、広告による収益は、インターネットを制するGoogleやFacebook、AppleやAmazonのものであり、テレビや新聞社の収益は圧迫される一方である。
朝日新聞社が5月26日に発表した決算で、11年ぶりの赤字に転落したことが報じられた。
朝日新聞社が26日発表した2021年3月期連結決算は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、売上高が前年比16・9%減の2937億7100万円、営業損益が70億3100万円の赤字だった。業績の動向などから、将来の利益を前提に税金の前払い分を資産として計上する「繰り延べ税金資産」を取り崩したため、純損益は441億9400万円の赤字となった。赤字は11年ぶり。(朝日新聞デジタル)
朝日新聞社は「コロナウイルス感染拡大の影響を受け」と説明しているが、事の本質はそんな表層的なものではない。
「新聞に金を払う価値はない」と現役世代思われていることが、本質なのだ。
もちろん、危機に瀕しているのはマスメディアだけではない。
むしろ中小の雑誌社、弱小インターネットメディアこそ、従来の「広告」ビジネスモデルが崩れた結果、稼ぐ手段を失っている。
デジタルに移行できなかった雑誌が続々と廃刊になり、「片手間」でやっていたサイト運営にも行き詰まり、にっちもさっちも行かないメディア企業が出てきてしまっている。
さらに、レガシーメディアの人間たちは、金儲けに疎い。
東洋経済オンラインの元編集長である佐々木紀彦氏は著書「5年後、メディアは稼げるか―Monetize or Die ?」の中で、メディア人は金を稼いだことののない人間の代表格だという。
メディア人は、公務員と同じく、自分でおカネを稼いだことのない人間の代表格といえます。メディア業界の人間ほど、ビジネスに疎い人間はなかなかいません(私を含むビジネス誌の記者・編集者でさえそうです)。「原稿料の金額を前もって聞くのは失礼」などという、一般のビジネスではありえない習慣が一部でまかりとおっているのも、いかにおカネについて真剣に考えてこなかったかの証左です。
今は「メディア」をやる人間こそ、どうやって稼がねばならないかを、考えなければならない時代なのにもかかわらずだ。
メディアが稼ぐ道は3つしかない
ただ、結論から言うと、現在のところメディアが稼ぐ道は3つしかない。
それは
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
1.広告
2.記事への直接課金
3.EC
の3つである。順に説明する。
1.広告
メディアにおいて、最もレガシーなビジネスが、広告だ。
媒体の一部を、広告枠としてスポンサーに貸し出すことによって、収益を得る。
ただし、高収益を保てるのは「広告枠を独占・寡占できる」という条件のもとに限定される。
従来のマスメディアは、広告枠を独占していたため、広告の収益性が高かったが、現在、インターネット上で広告枠を独占しているのは、GoogleとFacebookであり、個別のメディアがGoogleやFacebookに勝る広告モデルを確立できる望みは今のところ薄い。
個人のブログ程度であれば、一部をGoogleに貸し出す広告モデルは「副業」として成立する。
が、事業主や法人が運営するメディアが必要とする資金に対しては、収益性があまりにも低く、広告モデルの先行きは暗い。
むしろ今、力を持っているのはGoogleやFacebookの広告枠を「運用する」人々でありメディア側ではない。
ちなみに、この記事は2015年の記事であるが、東洋経済オンラインの収益性を記述している。
――東洋経済オンラインの収益はどこまで伸びていますか。「(編集長を昨年7月に)引き継いだ時点で月に3千万円ほどでした。それが12月には6千万円。広告単価が、安いながらもちょっとずつ上がっています。ネットワーク広告が増えて、ネイティブ広告も開拓を始めていて、これが成約に結びついていけば、大台にあがっていく。早く月に1億円にしたいと思っています」――8人の編集部員ですごい伸びですね。「ただ、月商1億円といっても、東洋経済オンラインには経営戦略、システム、広告など多くの社員が関わっています。8人だけでやっているものではないので、まだまだ十分に利益貢献できているというレベルではありません」
1億PV近くあるメディアで、月商は1億程度。
もちろん現在はかなり様子が違うとは思うが、編集8人体制、本社部門や広告営業などを賄うには余りにも少ない。
もちろん、Googleなどと戦うにはあまりにも貧弱すぎる。
これが日本で最も閲覧されているオンラインメディアの広告事業の現実だ。
2.記事への直接課金
記事への直接課金は、前述の広告モデルに比べて、より現実的な収益を約束する。
海外の大手新聞の多くが、この方式による収益化を主軸に据えていることからわかる通り、世界的にも、大手メディアは広告から記事への直接課金の方向へ舵を切っている。
だが、そのハードルは決して低くはない。
まず、日本で「記事への直接課金」で成功しているのは、大手新聞では日経だけだという事実が示す通り、記事へお金を払うのは「投資」「ビジネス」文脈において、回収が見込める場合のみである。
個人ブログについてもこれは同様で、収益化しやすいブログは「投資」「仮想通貨」「アフィリエイト」などの文脈で、すぐにリターンが見込めそうな題材である。
平たく言えば「金儲け」か「仕事」につながる記事は、有料でも購読されるが、一般的な報道、ニュースに対して、その記事制作コストに見合った金は落ちない。
したがって自社が運営するメディアが、上のようなリターンの見込める情報を流している場合に限り、直接課金の目があると考えてよい。
なお、「エンタメコンテンツ」で課金ができるのは、現在のところマンガだけ。BtoB、もしくはマンガ。これが、直接課金の目である。
だが、前述した「広告ビジネス」と同様に、直接の記事課金によって得られる収益は、広告枠を独占できていたころの収益にははるかに及ばない。
今後「マス」メディアは、インターネット上のプラットフォーマーに限られるというのが、本当のところだろう。
新聞社やテレビ局は、単なるコンテンツプロバイダーの一社になってしまう。いや、すでにそうなっている。
3.EC
さて、ECである。
ECと聞くと、Amazonのようなショッピングモール形式のECを思い浮かべるかもしれないが、それは狭義のECである。広義のECでは、ショッピングモール形式に限る必要はない。
例えば、コーポレートサイトで自社商品を販売しているのも、それは一種のECと言える。つまり「インターネット上の販売チャネル」はすべて、定義からしてECと呼ぶことができる。
そして、ECこそ「メディアの未来」を担うものであると私は見ている。
というのも、GoogleやFacebookに対して、圧倒的な優位性を持てるからだ。
たとえば何かを買いたい、と思った時に我々は何をするか。
Googleで検索するよりも、Amazonで検索をするほうが多いのではないか。
だが、Amazonですぐに買うわけではない。
めぼしい商品を見つけたら、公式サイト、あるいはSNSでも情報をとるのではないか。
そこにはGoogleやFacebook広告の入り込む余地はない。
純粋に、ECと、その周辺にある情報から、購買を決定する。
つまりECに十分な情報が存在していれば、我々はそこで広告を経由せずに、物を買うことができる。
従来、メディアは「記事を閲覧すること」に対して、課金を発生させてきた。
広告しかり、記事への直接課金しかりである。
つまり、売り物は「情報」に限られていた。
しかし、本当に「情報」だけを売り物にして良いのだろうか?
もちろん、そうではない。
メディアは、人が集まる。
そして、人が集まれば、商機が生まれる。
商機があれば、ほぼ何の商品でも扱うことができる。
例えば日経新聞はすでに、ECサイトを持っていることはご存じだろうか。

中立性の観点からか、あまり日経はこれを表に出さないが、すでに彼らはECを有している。
ただ現在はBtoC商材が多いため、「クラウドファンディング」という特殊な領域でしかECをやっていない。
が、BtoB商材であればもっと相性は良いだろう。
例えばキーエンスという、センサーの会社がある。
平均給与が日本で最も高い会社の一つだが、マーケティングが強いことで知られる。
そしてこの会社、実はメディアを運営している。
その一つが以下のサイトだ。

俗にいう「オウンドメディア」と呼んでもよいが、彼らはほかにも複数のメディアを運営しており、それぞれに記事が投稿されている。
では、彼らはなぜメディアをやっているのか?
広告で儲けるためではない。
記事への課金もしない。
もちろん、自社製品を売るためだ。
ここは、キーエンスが運営する「EC」であり、あちらこちらに商材へのリンクと、資料のPDFダウンロードができるようになっている。

このように、メディア自身が「EC化」すれば、メディア事態でもうけを出す必要がない。
「専門誌」と考えれば、これは未来のメディアの姿の一つだと十分に考えることができるだろう。
Books&AppsのEC化
もちろん、我々もBooks&Appsで、同様のことを行っている。
例えば以下の告知は、すべての記事の下に張られているPR欄だが、弊社のサービスに関する資料をダウンロードできるようになっている。

「自社メディア」で、自社商品の営業を行うのであるから、AmazonがAmazonブランドの商品を売るのとさして変わりはない。
だが、Books&Appsはキーエンスとは異なるメディア運営をしている。
最大のちがいは、「記事」と「商材」が、Books&Appsにおいてはあまり関係がないことだ。
例えば、上のダウンロードリンクは、「サイボウズは、理想の取締役会を作れるか」という記事の下に張られている。

このように言うと、よく「商材と関係のない記事に、PRを張っても、まったく問い合わせにつながらないのでは?」と聞かれる。
実は、まったくそんなことはない。
実は、商材と関係のない記事でも、PR欄は機能する。
どの程度問い合わせがあるのかと言うと、資料ダウンロードであれば、上の記事のページビュー数に対して、0.1%程度。
つまり記事が1000回読まれると、1回のコンバージョンにつながる。
これが「無料セミナー」だと、0.05%~0.1%程度。
さらに「書籍のプレゼント」や「トライアルサービス」などの強いフックがあると、2%~3%まで跳ね上がる。
こうして記事を置いておくだけで、一定のページビューがとれ、それが自動的に案件を生み出すのだから、時間がたてばたつほど、効率の良い、営業活動となる。
これが「メディア」を所有している会社が、かつそこでマネタイズを行うための、最強の手段である。
「メディア専業」にこだわる必要は全くない
つまり、将来的に「メディア」と言うのは、収益性の観点から見て
1.GoogleやFacebookのような、インターネット広告枠を独占するプラットフォーマー
2.直接記事に課金できる、小規模なBtoB経済メディア、投資メディア
3.「メディア」を専門誌のごとく運用し、自社商品の販売をもくろむ、企業群
の3つに収れんする可能性が非常に高いと、我々は考えている。
そして、メディア専業なのは2.のみ。
収益化をもくろむほとんどのメディアは、何かしらの商材をもって、メディア運営にあたることになるだろう。
—
【お知らせ】
Books&Apps及び20社以上のオウンドメディア運用支援で得られた知見をもとに、実際我々ティネクト(Books&Apps運営企業)が実行している全48タスクを公開します。
「成果を出す」オウンドメディア運営
5つのスキルと全48タスク
をプレゼント。
これからオウンドメディアをはじめる企業さま、現在運用中の企業さま全てにお役に立つ資料です。ぜひご活用ください。
資料ダウンロードページはこちら↓
https://tinect.jp/library/5skills48tasks/
メールアドレス宛てに資料が自動送信されます。